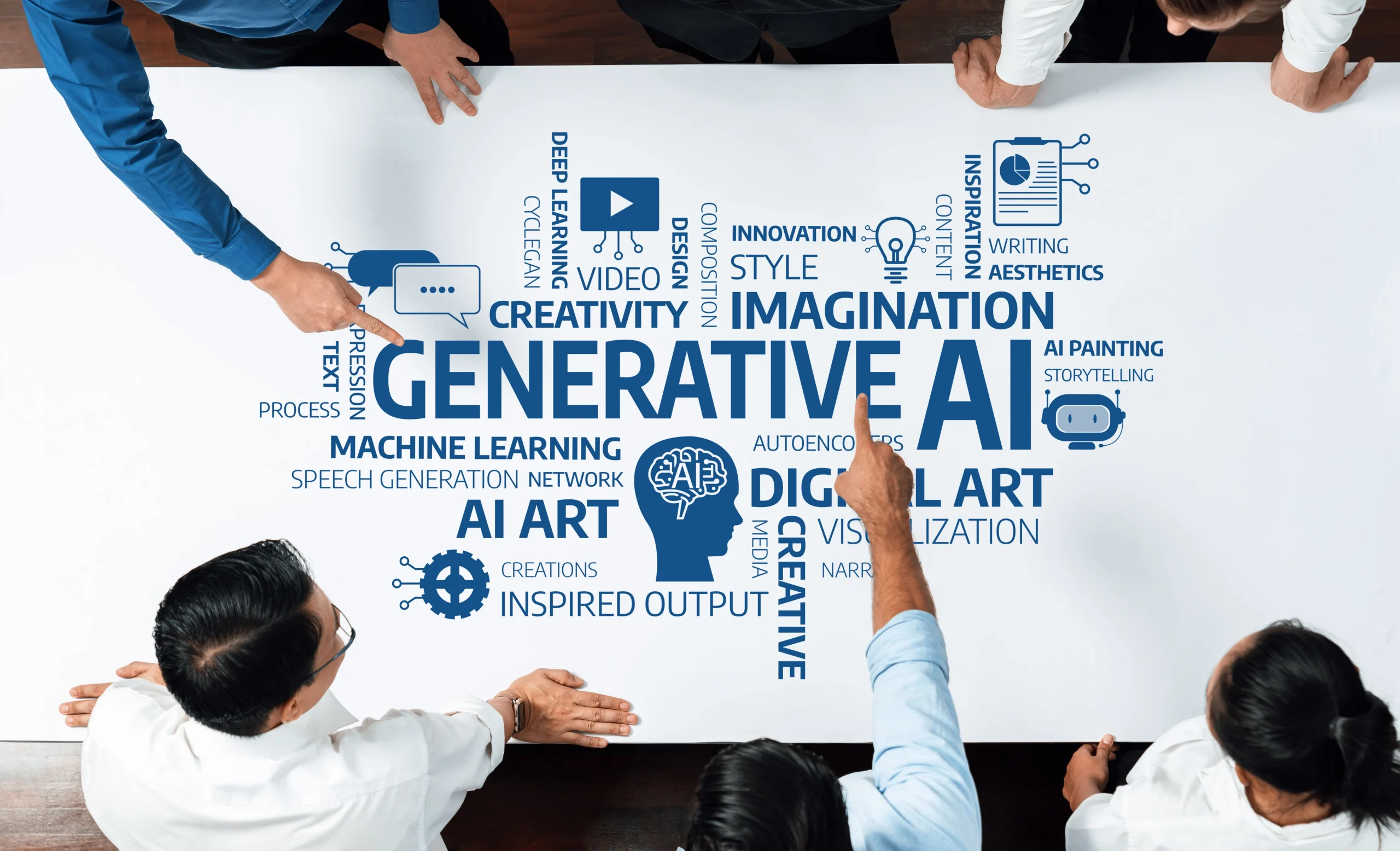なぜ今、スクール運営に生成AIが求められているのか
業務効率化と人的負担の軽減が急務に
少人数で運営されている学習塾や習い事教室では、講師が事務作業や各種保護者対応まで兼務しているケースが少なくありません。もっと言うと業務の境界がなく、スクール運営に関わるほとんどの作業を行うケースまであります。
そのため、連絡業務や教材準備など運営業務に多くの時間を取られ、本来注力すべき授業準備や生徒分析など教育活動に時間を割けないという問題を抱えているスクールが多くあります。
無料・低価格で生成AIツールを即導入できる時代
ChatGPTやNotion AIといった生成AIツールは、ノーコード(プログラミング言語を使用せずに)で使用できるものも多いので、専門知識がなくても簡単に導入・活用が可能です。しかも、無料または月額3,000円程度の低価格な料金で始められるため、小規模なスクールでも手軽に業務改善を進められます。
それでは実際にどのようなAIツールが、塾や教室などのスクールの、どういった場面で活用できるか紹介していきます。
スクール運営で使える生成AIツール活用アイデア10選
1. 保護者への連絡文書作成
毎月のお便りやイベント概要資料など、保護者への連絡文書を作成する機会は多くあります。また、保護者面談での議事録など、文書化する必要のある業務は多くあります。
ChatGPTやNotion AIを使えば、日時・目的・内容などのキーワードを入力するだけで、丁寧かつわかりやすい簡単な文章案を自動生成できますし、細かく指示すれば目的に近い文書も作ってくれます。
文書作成が得意な方の場合は、生成された文書案を微修正するだけで良いので、作業が大幅に簡素化できますし、苦手意識がある方にとっては、文書を一から作らなくて良くなるので大きな助けになります。
2. 授業テキストやプリント案の生成
授業の要点を整理した資料作成は、時間と手間がかかる作業です。
Microsoft CopilotやGammaなどのAIツールを使えば、単元や学年、内容を指定するだけで、構成案やスライドの骨子を自動で提案してくれます。講師はその案をもとに加筆・修正するだけで済むため、大幅な時短につながります。また、AIへの指示次第でテキスト(教科書)も作成可能です。
3. 生徒への個別フィードバック文や「所見」の作成
成績所見や日々の指導報告は、全生徒分ありますので、作成作業の量が多くなります。生成AIを使えば、生徒の学習進度や学習状況など、元となる情報を入力するだけで、丁寧なフィードバック文案が生成できます。最後に講師がチェックし、必要な修正を加えれば、質を保ちながら作業工数の削減が実現できます。
4. SNS・ブログ投稿の文・画像案生成
スクールの魅力を発信するためのSNS運用も、AIがあれば負担を減らせます。ChatGPTで投稿文を生成し、Canva AIでビジュアル素材を作成することで、プロ品質の投稿が短時間で完成します。イベントやキャンペーンの告知にも効果的です。
また、文字数を指定して文書生成させることもできるので、スクールサイトに掲載するテキストの作成など、文字数を調整したテキスト作成はかなり楽になります。
5. 講師間の共有メモ・議事録の要約
ミーティングや面談内容をただ記録するのではなく、要点だけを整理して共有したい場面でも生成AIは力を発揮します。
たとえば、Geminiを活用すれば、録音データやメモから議事録を自動で要約でき、作成の手間を大幅に軽減できます。また、オンラインの場合でもTeamsやZoomでは、会議終了時にテキストと映像データが生成されるので、その情報を生成AIに読み込ませることで、要約や議事録作成が簡単にできます。
さらに、会議中の雑談を除いた要点だけの抽出も可能です。こうした生成AIの活用方法は、特に多い使い方となります。
6. 簡単な確認テスト・小テストの作成
学習内容の理解度を測るための小テストも、AIで自動生成が可能です。例えば「小学4年生の漢字」「英語の過去形」などを指定するだけで、選択問題や穴埋め問題を複数提案してくれます。忙しい時でも素早く準備できます。
7. 生徒対応用FAQ・マニュアルのひな形作成
「授業の振替はどうする?」「教材はどうやって買う?」「振替のルールは?」といったよくある質問に対して、統一された対応をしたい場合にもAIが活躍します。代表的な問い合わせと、その回答をあらかじめ整備しておくことで、対応品質が安定し、問い合わせ対応も効率化されます。
また、生成AIを活用したアプリ開発支援プラットフォームも存在し、ノーコードで独自のチャットボットを作成できるだけでなく、Webサイトへの埋め込んだ活用も可能です。
8. カリキュラムやレッスン構成のたたき台
新年度や新コースの立ち上げ時には、年間のカリキュラムを組む必要があります。Notion AIでは、目標や期間などを入力することで、週ごとの授業案や到達目標のたたき台となる案を生成することが可能です。講師はそのたたき台をもとに内容を調整するだけで、作業時間を短縮できます。
9. 書類や契約書の草案作成補助
入会申込書や保護者同意書、利用規約といった書類の初期ドラフトもAIで生成可能です。ベースとなる文書をAIに作成させたうえで、法的確認や細部の調整を加えることで、ミスを減らしながら作業効率を高められます。
※契約書などの法的な書類は必ず専門家の確認の上ご活用ください。
10. 新規事業や集客案のブレスト支援
スクールの成長には、新しいコース設計や集客施策の立案が欠かせません。ChatGPTやGeminiに「〇〇向けの新講座を作りたい」「地域の親子層にアピールしたい」などと入力すれば、多角的なアイデアが得られます。ブレインストーミングのパートナーとしても優秀です。
導入時の注意点と導入ステップ
無料版と有料版の違いを理解する
多くの生成AIツールは無料で試すことができますが、本格的な業務活用を目指す場合は、有料版への切り替えも視野に入れるべきです。有料版では以下のような機能面の強化が期待できます:
・回答精度の向上:より長く複雑な文章にも対応し、文脈理解や表現の精度が高まります。
・履歴の保存・参照機能:過去のチャットや作成物を後から見返せるため、継続的な改善や再利用が可能になります。
・カスタマイズの柔軟性:自社の業務内容やトーンに合わせたプロンプト設定や、チャットボットの見た目・動作の調整などが行えます。
・使用制限の解除:入力文字数や応答回数の制限が緩和され、安定した業務利用が可能になります。
また、有料プランでは、セキュリティ面の機能強化や商用利用に関する可否や条件が設けられていますので、実際に業務で活用する際は、各ツールの利用規約を事前にしっかり確認し、ツール選定しましょう。
その上で、まずは無料版で手軽に試しつつ、必要に応じて有料プランへ移行するという段階的な導入がおすすめです。
「1業務1ツール」から始めるのが現実的
いきなりすべての業務でAI活用しようとするのではなく、まずは「保護者への連絡文作成」など、簡単で汎用性の高い業務から導入するのが現実的です。
生成AIツールにはさまざまな種類があり、それぞれ得意分野や特徴が異なります。すべてを完璧に把握する必要はありませんが、「何ができるか」「どの程度の精度か」など、ツールの特性を理解したうえで選ぶことが大切です。
また、AIツールは進化のスピードが非常に速く、「以前はできなかったことが今は可能になっている」ことも珍しくありません。常に最新情報をキャッチしましょう。 導入後も定期的に見直しと効果検証を行い、必要に応じてツールを切り替える、用途を広げるなど、段階的に活用範囲を拡大していくことが、成功への近道となります。
まとめ:AIを“スタッフの一員”として育てるつもりで
生成AIは、正しく使えばスクール運営の効率化や質の向上に大きく貢献するツールです。ただし、ツールに頼り切るのではなく、「人が使いこなす」という視点が重要です。
最初は小さく始めて、成果を確認しながら徐々に定着・拡大させる「スモールスタート → 定着 → 拡張」という段階的なステップで、生成AIを、スクール運営を支える“スタッフの一員”として、ぜひ取り入れてみてください。
個人経営や小規模なスクールでこそ、小回りが利いてすぐに便利さを体感できると思います。
SCHOOL MANAGERでは、塾や教室をはじめとする各種スクールを対象に、業務自動化(DX)支援やコンサルティングを通じて、日々の業務負担の軽減や効率化のサポートや、生成AIを活用した学習サポートアプリの開発も行っています。
参考までに、英語学習AIアプリを一般公開していますので、ご確認ください。
なお、SCHOOL MANAGER未導入のスクールでも、業務効率化など業務サポートに関するご相談や導入は可能です。
「生成AIについて一から教えてほしい」というようなスクールのご担当者様からのご相談にもお応えしています。いまさら聞けないと思わずに、お気軽にお問い合わせください。